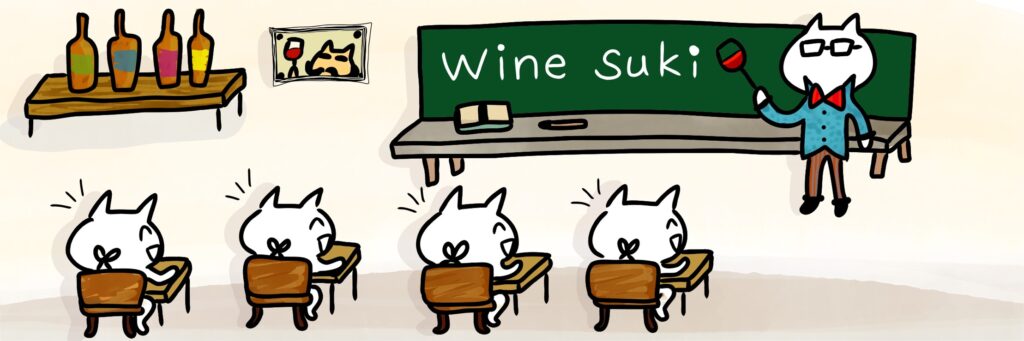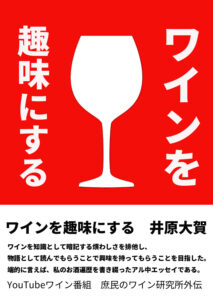ワインの基礎本や指南書でよく目にする、
「初心者はまず、「ボルドー」と「ブルゴーニュ」の違いを覚えなさい。」
これ、「庶民のワイン研究所」の見解からすれば、ワインの敷居をめちゃくちゃ高めている「禁句」用語なんですよ。。
まぁね、、、、、、ワイン界の重鎮達の言いたいことも、わからんでもないです。
「関西のうどんと関東のうどんは出汁が違う。」
きっとこれを言いたいんだと。
しかし、濃い味付けの出汁、繊細な出汁かなんて、飲まなくても区別つきますから(断言)。
まずは、広さ(範囲)という概念で考えてみましょ。
※ちなみにAC=AOC=原産地呼称保護=この土地で造られましたといった意味※
- ブルゴーニュ地方の面積約30km2、
- ボルドー地方の面積は約50km2、
これを日本に置き換えてみると、
- 近畿地方の面積約33km2
- 東北地方の面積約65km2
これが何を意味するか、、、
すなわち、関西牛なんか誰も買わないでしょ?笑
そう、名産品として食べたいのは「松坂牛」や「神戸牛」
東北のお米じゃなくて秋田の「あきたこまち」
東北のりんごじゃなくて「青森のりんご」
これを海外に輸出するする場合に置き換えると、
東北のりんごは有名だから美味しいよ(福島産)
関西の牛肉はお金持ちのステータス(奈良産)
※福島県民さん、奈良県民のみなさん、決して悪意はありません※
これを念頭に入れておくと、なんか騙されている気分がしませんか?
ワインの原料となるブドウも『産地』が味わいの9割をしめると言われており、ボルドー(ブルゴーニュ)の広い、身元がわからないブドウで造られたワインが
「美味しいわけないでしょ。』(主観含む)
じゃ、ボルドーやブルゴーニュってなんなの????
って思われた方。少し振り返って考えてみましょう。
近畿、東北=青森、兵庫→神戸、三重→松坂
そうです、日本で例えると県、市、町に該当する、「村名」「畑名」の小区画呼称が存在するのです。
読者の声
「でもな、、、、いちいち、「村名」や「畑名」覚えるのめんどくさいなぁ。。。。」
安心してください。
.
.
.
覚えたとしても
.
.
「庶民には買えないような価格ですから!!!!!!!!!」
.
補足:(松坂牛毎日食べる人いないでしょ。)
.
.
じゃ、初心者はどんなワインをどんな風に買えば良いの?
ブルゴーニュやボルドーは飲めないの???
ワインは貴族の飲み物なの????
答えはNo!!!
パート2以降でその問題を解決させますので^ – ^
まとめ
ワイン界がイメージ戦略として「ボルドーやブルゴーニュ」と言い出した結果。
下記の現象が起こっているのです。
- 小区画の銘醸地を広範囲名前で宣伝し、
- さも格式が高いワインのように見せかけ、
- 先入観で買い物をさせ、
- わかりやすい「ボルドー!やブルゴーニュ!」でワインを売り出し、
- 小売店は毎日のように「ボルドーやブルゴーニュ」の安売りをする。
- もちろん叩き売りされるワインは
- 粗悪なものが大半=不味い。
- 不味い=ワイン嫌い の悪循環、悪い図式に落ちいてしまう。。。。
パート2以降の予告内容です。
「アルパカを侮るな。最下層を知ってからがスタートライン」(公開済み)
「ACボルドーは「シャトー」で選べ!」
「ACブルゴーニュ攻略法の鍵は「生産者とドメーヌ」」
「ウェルカム、トゥ、ニューワールド」
「ねぇねぇ、ローヌやロワールって知ってる???」
「ビオワイン最強の土地、未認証の「プロバンス」」
「格式と庶民性の兼ね合わせ「イタリア」へようこそ。」
「最終章「本物はボルドーとブルゴーニュにあり」」
をお送りします。ご期待ください。



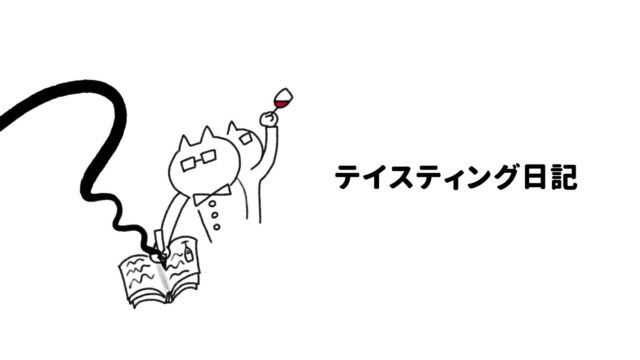
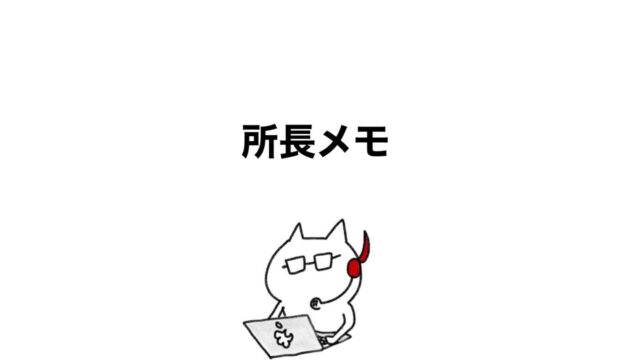



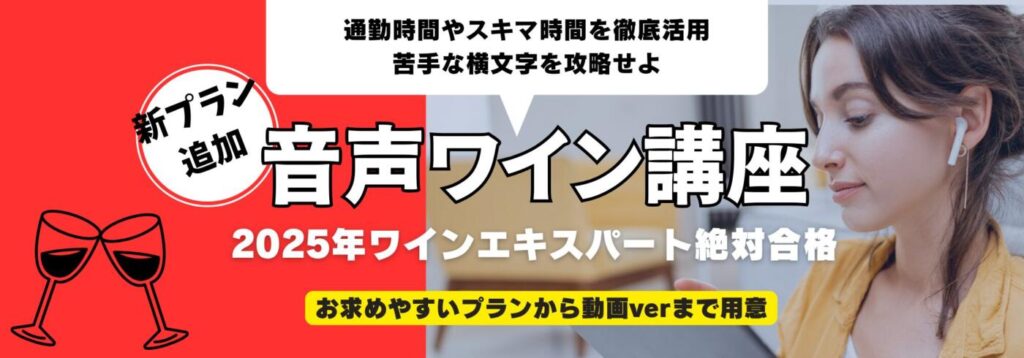

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b8188a8.c3f11a24.1b8188a9.33748e7a/?me_id=1335910&item_id=10006114&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-naotaka%2Fcabinet%2Frakuten50%2Fw657n40_500-1m.jpg%3F_ex%3D100x100&s=100x100&t=picttext)